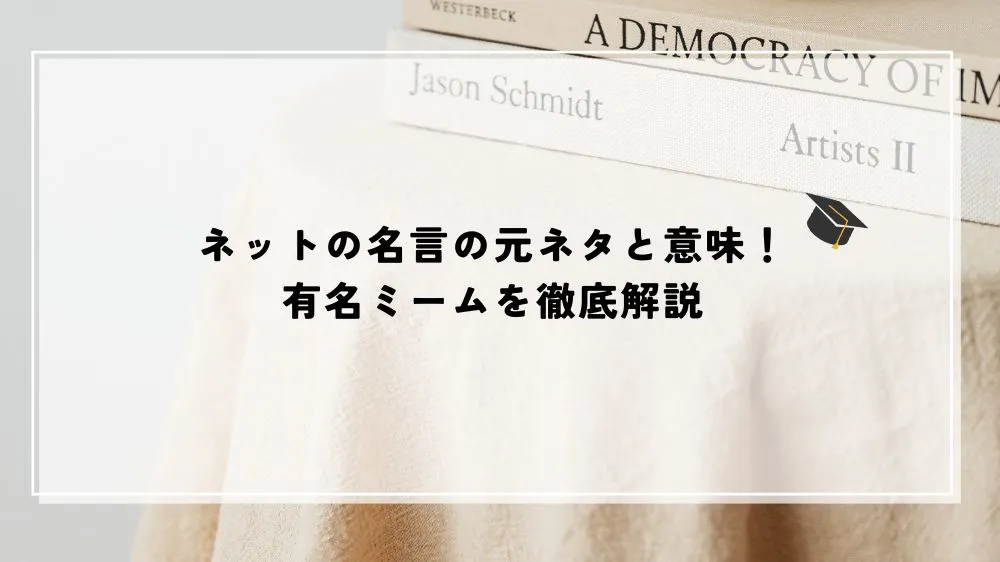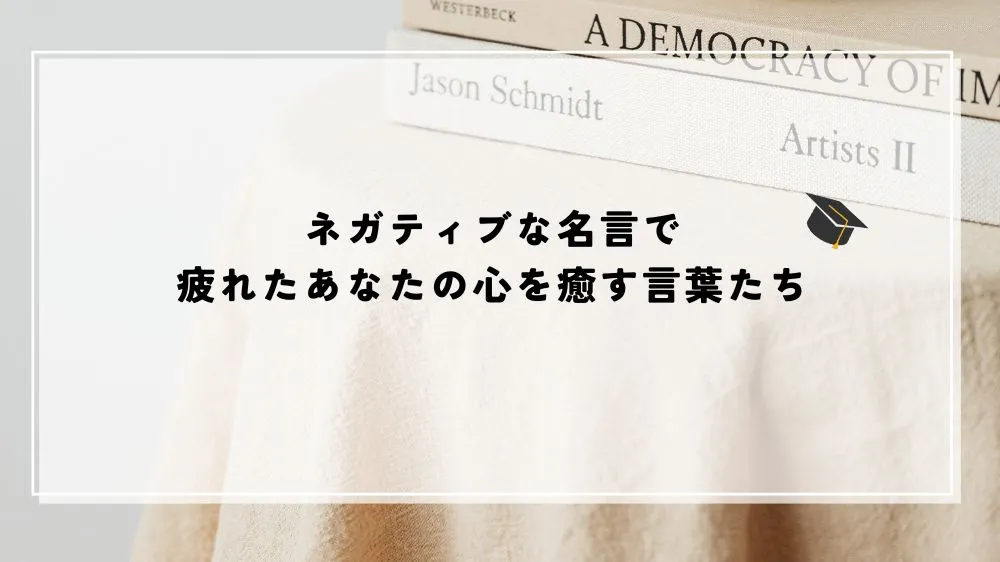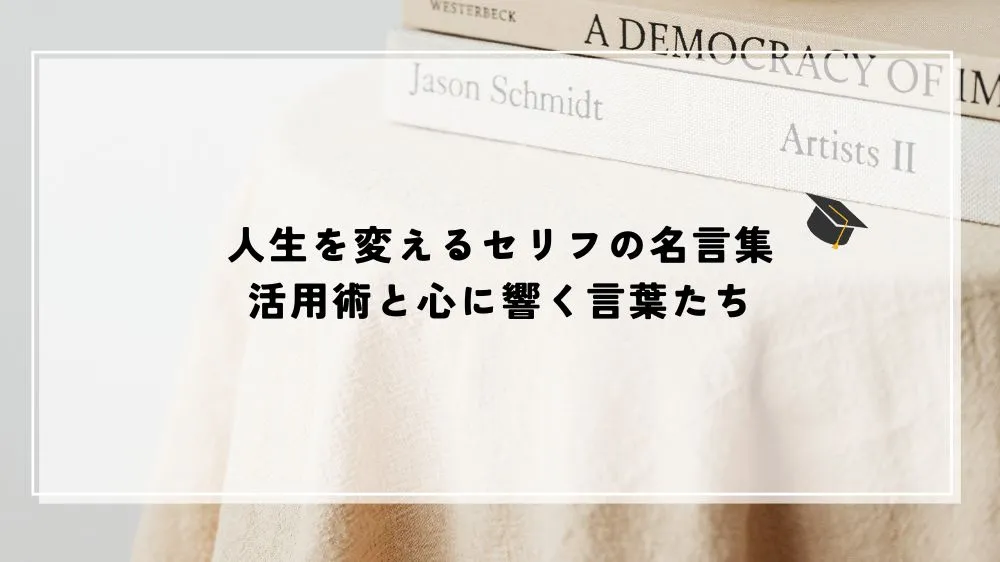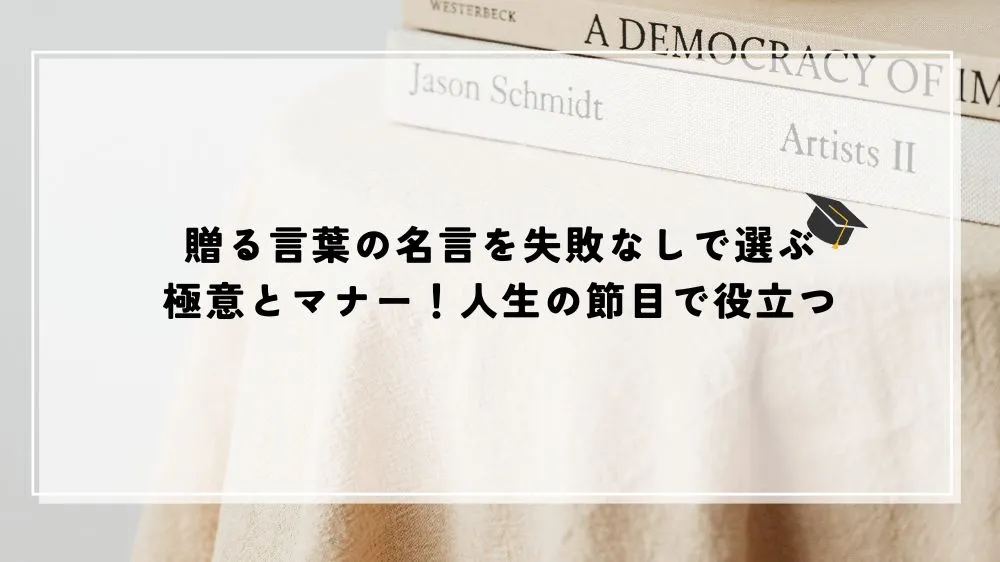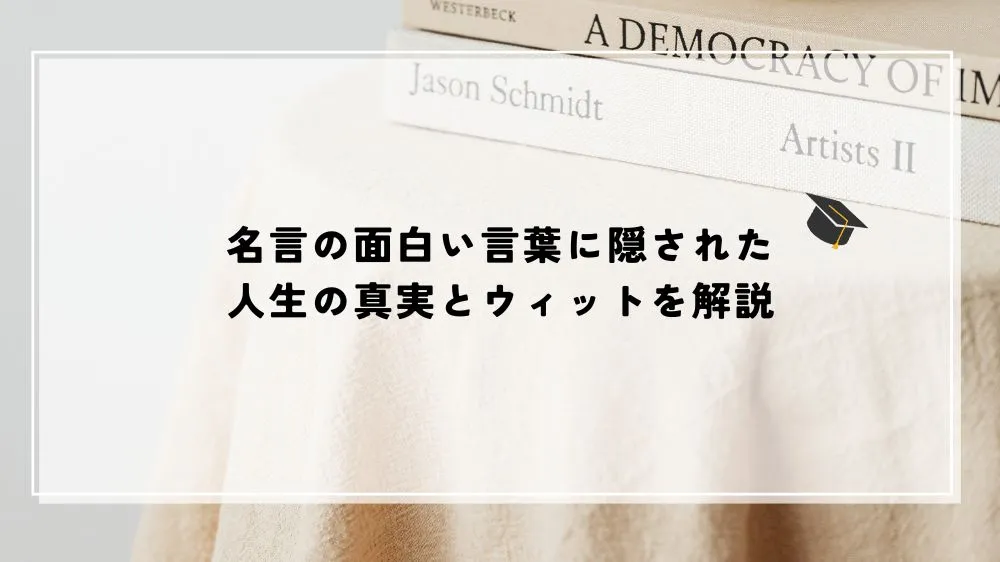「仁 名言 ペニシリン」というキーワードで検索されたあなたは、ドラマ『JIN-仁-』で描かれた感動的なシーンや、心に残るセリフを思い出しているのではないでしょうか。
南方仁が江戸時代にペニシリンをもたらしたエピソードは、物語の大きな転換点であり、彼の医師としての信念が最も強く表れた瞬間でした。
この記事では、仁のペニシリンに関する名言が、その奇跡の薬とどう結びつき、江戸の人々の運命を変えていったのか、その感動の軌跡を詳しくたどります。
仁のペニシリンに関する名言やペニシリン 仁の作り方の背景、そしてペニシリン薬効ありと証明される感動的な場面を深掘りします。
ペニシリンにございますのものまねといった印象的なセリフが生まれた背景にも触れていきます。
また、コロリでございますという言葉が持つ当時の絶望的な意味や、ペニシリンは何に効く薬だったのか、ドラマ「仁」でペニシリンが出てくるのは何話だったかについても詳しく解説します。
さらに、綾瀬はるかさん演じる咲のセリフやドラマ「仁」で坂本龍馬が言った名言は?といった疑問、そして歴史的にペニシリンを作った日本人は誰なのか、といった豆知識まで、幅広くご紹介します。
この記事の内容
- 『仁』とペニシリンを巡る名言の背景
- ペニシリンの作り方や登場話数
- 「コロリ」や「ものまね」名シーンの意味
- 坂本龍馬や橘咲の心に残るセリフ
仁の名言とペニシリンの登場
ポイント
- 仁のペニシリンの作り方を解説
- ドラマ「仁」でペニシリンは何話に?
- ペニシリン薬効ありと証明
- コロリでございますという言葉の意味
仁のペニシリンの作り方を解説
ドラマ『仁』において、南方仁は江戸時代には存在しなかった抗生物質ペニシリンを、ゼロから精製することに挑みます。
当時の江戸では、小さな傷が化膿しただけで命を落とすことも珍しくなく、特に遊郭では梅毒が不治の病として多くの人々を苦しめていました。
仁にとって、この状況は耐え難いものであり、現代医療の知識を使って人々を救いたいという強い意志が、ペニシリン精製という無謀とも思える挑戦に向かわせました。
彼の「命を守るためにはどんな方法でも試さなければならない」という名言に象徴されるように、その道のりは困難を極めます。仁はまず、現代の知識を頼りに「青カビ」を集め、そこからペニシリンを培養しようと試みました。
当初、仁は自らカビを集め、原始的な方法で培養を試みますが、雑菌の混入や培養環境の不安定さから、十分な量のペニシリンを安定して得ることはできませんでした。
試行錯誤が続く中、転機となったのは、緒方洪庵の意志を継いだ醤油屋・浜口儀兵衛(ヤマサ醤油)との出会いです。仁は、醤油の醸造に使われる「麹菌」を安定して大量に培養する技術に着目します。
この江戸時代から続く発酵技術が、最先端の医療であるペニシリン精製と結びつくという、ドラマならではの熱い展開です。仁は浜口儀兵衛の醤油蔵の協力を得て、ついにペニシリンの安定的な精製に成功するのです。
これは、現代の知識と江戸の技術が融合した奇跡的な瞬間でした。
補足:実際のペニシリンの発見
歴史的な事実として、ペニシリンは1928年にイギリスの細菌学者アレクサンダー・フレミングによって発見されました。ドラマのように、アオカビが細菌の増殖を抑えることから偶然発見されたことは有名です。仁は、この歴史を知っていたからこそ、江戸という何もない環境でも、青カビから薬を作るという発想に至ることができました。
ドラマ「仁」でペニシリンは何話に?
ペニシリンの製造と、それがドラマチックに使用される一連のエピソードは、第1期(2009年版)の主に第4話から第6話にかけて描かれています。
この部分は、仁が江戸の医療に本格的に革命をもたらす、物語の大きな山場の一つです。
- 第4話:仁が緒方洪庵と出会い、医学所での西洋医学の限界、そして梅毒に苦しむ人々(特に夕霧の前段階)を目の当たりにし、仁は現代医療の知識を使う決意を固めます。ここでペニシリンの必要性を痛感します。
- 第5話:ペニシリン精製の具体的な苦労が描かれます。青カビ集めや培養に苦心し、咲や他の医師たちの協力(あるいは懐疑)の中で、仁が孤軍奮闘する様子が中心となります。
- 第6話:クライマックスです。精製されたペニシリンが、末期の梅毒に侵された花魁・夕霧に初めて投与されます。このシーンは、「神の領域」に踏み込むことへの葛藤と、医師としての使命感が交錯する重要な場面として描かれます。
この第4話から第6話にかけての展開が、仁の医師としての覚悟を江戸の人々に示し、その後の「仁友堂」設立への大きな流れを作っていきました。ペニシリンを巡る物語は、シーズンを通しての重要なテーマとなっていきます。

手元に置いておきたい方には、DVD/Blu-ray BOXもおすすめです。
ペニシリン 薬効ありと証明
ドラマでペニシリンの「薬効あり」と江戸の医師たちに強烈に印象付けたのは、第1期第6話の夕霧花魁への投与シーンです。
夕霧は、仁の友人である野風が憧れていた伝説の花魁でしたが、末期の梅毒に侵され、もはや手の施しようがない状態でした。周囲の医師たちが「得体の知れない水」と疑う中、仁は自らの信念に基づき、完成したばかりのペニシリンを彼女に注射します。
その結果、高熱が下がり、朦朧としていた意識がはっきりと戻るなど、まさに「奇跡」と呼べるほどの劇的な回復を見せます。この瞬間、ペニシリンの薬効は誰の目にも明らかになりました。
残念ながら、ペニシリンは細菌を殺す薬であり、すでに梅毒によって破壊されてしまった臓器や組織を元に戻すことはできません。
病状が進行しすぎていたため彼女の命を救うことは叶いませんでしたが、この出来事はペニシリンの薬効を江戸の医師たちに証明する決定的な瞬間となりました。この後、ペニシリンは怪我による感染症患者など、多くの命を救う切り札となっていきます。
コロリでございますという言葉の意味
「コロリでございます」というセリフは、当時の江戸で最も恐れられた病の一つを指す言葉です。この「コロリ」とは、現代でいう「コレラ」のことです。「虎狼痢」という恐ろしい漢字が当てられることもありました。
コレラは、コレラ菌に汚染された水や食物を通じて口から感染します。体内に入ると菌が毒素を出し、その影響で腸が水分を際限なく排出してしまいます。
「米のとぎ汁」のような便が特徴で、激しい下痢と嘔吐により、数時間から1日で死に至ることもあるほど急激な脱水症状を引き起こします。(参照:厚生労働省検疫所 FORTH「コレラについて」)
ドラマの中で「コロリでございます」という言葉は、当時の医師たちが診断を下した時点で、すでに手の施しようがない「死の宣告」を意味していました。仁は、このコレラ治療のために、現代医療の知識である「経口補水液」や「点滴」(生理食塩水の再現)を江戸で再現しようと奮闘します。このエピソードは、ペニシリンとは別の形で、仁がもたらした医療知識が江戸の絶望的な状況に光をもたらす様を描いています。
なぜ「コロリ」と呼ばれたか
「コロリと死ぬ」という急激な症状の進行に加え、その恐ろしさから「虎(とら)」や「狼(おおかみ)」に襲われたかのように突然死ぬ病、という意味で「虎狼痢」という字が当てられたとも言われています。
仁とペニシリンにまつわる名言
ポイント
- ペニシリンにございますのシーン
- ペニシリンでございます ものまねセリフ
- 綾瀬はるか演じる咲のセリフ
- ドラマ「仁」で坂本龍馬が言った名言は?
- ペニシリンを作った日本人は誰か
- 仁の名言とペニシリンの医療理想
ペニシリンにございますのシーン
「ペニシリンにございます」というセリフは、仁が苦労の末に精製したペニシリン(薬液)を、江戸の医師たちや患者に示す際の「ペニシリンでございます」というセリフから派生した言葉、あるいはそのシーンそのものを指していると考えられます。
このセリフが登場するのは、仁が現代医療の切り札としてペニシリンを江戸の人々に提示する、緊張感と希望が入り混じる重要な場面です。
当時の人々にとっては「青カビから作った得体の知れない水」でしかありません。
しかし、仁にとっては「多くの命を救うことができる希望の薬」です。
このセリフは、単なる薬の説明ではなく、現代医療の知識という「異物」を、江戸という世界に受け入れさせるための、仁の覚悟とプレゼンテーションの始まりを告げる言葉だったのです。
そのギャップと、仁の真剣な思いが凝縮されたセリフであり、この薬が江戸の医療に革命をもたらすことを象徴するシーンでした。
ペニシリンでございます ものまねセリフ
「ペニシリンでございます」というセリフは、ドラマのシリアスな展開とは対照的に、放送後、お笑い芸人によるモノマネのネタとしても有名になりました。
これは、南方仁を演じた大沢たかおさんの、極度に真剣で、どこか浮世離れした独特の間(ま)と抑揚が、視聴者に強烈な印象を残したためです。
「ペニシリン」という聞き慣れない単語と、そのシリアスすぎる言い回しのギャップが、ユーモラスなものまねの対象として最適だったのです。

ドラマ内のユーモラスなシーンとして、仁が他の登場人物のモノマネをする場面もわずかにありますが、視聴者によく知られている「ものまね」は、仁自身のこの「ペニシリンでございます」というセリフを指すことがほとんどです。
綾瀬はるか演じる咲のセリフ
綾瀬はるかさんが演じたヒロイン・橘咲(たちばな さき)は、武家の娘という立場を捨て、仁の助手として医療の道に進むことを決意します。彼女のセリフには、葛藤と強い決意、そして仁への深い思いやりが込められています。
特に印象的な名言の一つが、コレラ治療などで疲弊する仁を励ます場面の「先生と、先生の医術とお会いしてから、咲はなにやらいろんなものが以前よりは明るく見えます。脈打つ心の音を感じます。咲は、、、、生きておりますよ」というセリフです。
これは、コレラ蔓延という絶望的な状況下で、仁自身も疲弊し、時には医療の限界に打ちのめされそうになる中で発せられた言葉です。
仁がもたらした医術が、ただ病を治すだけでなく、咲自身の生きる意味や世界の見え方まで変えたことを伝える、仁への最大の感謝と励ましの言葉でした。
橘咲のその他の名言
- 「先生には、おられるのでございます。その方の為になら鬼にもなろうという方が。」(仁の未来の恋人・未来の存在を察し、自らの恋心に蓋をしようとする切ない場面の言葉)
- 「らちのあかぬことを悩むのはやめたのです。」(武家の娘としての安定した未来(縁談)を捨て、医療という未知の道へ進むと決めた覚悟の言葉)
- 「人として張らねばならぬ意地でございました。」(縁談を破談にしたことへの後悔と、医師の助手としての誇りを語る、彼女の成長を示すセリフ)
ドラマ「仁」で坂本龍馬が言った名言は?
内野聖陽さんが豪快かつ魅力的に演じた坂本龍馬も、数々の名言を残しています。彼は仁の親友として、時には導き、時には支えられる存在でした。
龍馬の名言として特に有名なのが、「死んでいったもんらに報いる方法は、一つしかないち思わんかえ?もっぺん、生まれてきたい。そう思える国にすることじゃき」というセリフです。
このセリフは、仁が「歴史を変えてしまう」ことへの恐れと罪悪感に苛まれている際に、龍馬がかけた言葉です。未来から来た仁の医療が、多くの命を救っているという「事実」を肯定し、それを未来の国づくりに繋げようとする龍馬のスケールの大きさが表れています。
また、完結編(第2期)のクライマックスの一つで、仁が未来へ帰るかもしれないと知った龍馬が語る「わしらは、ずっと、先生と共におるぜよ。見えんでも、聞こえんでも、おるぜよ。いつの日も、先生と共に!」というセリフも、時代を超えた二人の深い友情を感じさせ、多くの視聴者の涙を誘いました。
たとえ歴史が変わっても、仁と出会い、共に生きた「魂」は消えないという、二人の深い絆を象徴する言葉です。
ペニシリンを作った日本人は誰か
ドラマ『仁』では南方仁が江戸時代にペニシリンを精製しましたが、これはもちろんフィクションです。歴史上の事実として、日本国内でペニシリンの製造(国産化)に成功したのは、昭和時代(1940年代)のことでした。
当時、アメリカやイギリスではすでにペニシリンが実用化されていましたが、日本は第二次世界大戦中、医薬品の輸入が困難になり、負傷した兵士や国民を救うために抗生物質の国内製造が急務となりました。
多くの研究者がペニシリンの培養に挑みましたが、その国産化に大きく貢献した人物の一人として知られるのが、森永製菓の研究所にいた稲垣長治(いながき ちょうじ)氏です。
彼は、戦時中に保存されていた乾燥ブドウから偶然、強力なペニシリンを作る青カビを発見し、これが日本のペニシリン量産のきっかけになったという逸話が残っています。(参照:森永製菓株式会社「森永の歴史:ペニシリンの製造」)
ドラマは壮大なフィクションです
『仁』の物語は、この史実よりも約80年も早く、南方仁という一人の医師がペニシリンを日本にもたらすという、壮大な医療フィクションです。仁が醤油蔵の技術を応用して奮闘する姿は、史実でペニシリン国産化に尽力した先人たちの苦労と情熱を、別の形で描き出したものと言えるかもしれません。
仁の名言とペニシリンの医療理想
南方仁が江戸時代にもたらしたペニシリンは、単なる薬ではありませんでした。それは、「どんな時代の人間であっても、救える命は救いたい」という、医師としての普遍的な、そして根源的な理想の象徴です。
「神は乗り越えられる試練しか与えない」という仁自身のセリフに励まされながら、彼はペニシリン精製という試練を乗り越えました。仁の名言とペニシリンのエピソードは、現代に生きる私たちにも、命の尊さと諦めないことの大切さを強く問いかけています。
ドラマ『JIN-仁-』とペニシリンにまつわるエピソードは、単なる医療ドラマを超えた深い感動を与えてくれます。この記事で解説した「仁 名言 ペニシリン」に関する情報をまとめます。
記事を読んで、もう一度ドラマ『JIN-仁-』を観たくなった方も多いのではないでしょうか。
ペニシリンを巡る名言や、仁・咲・龍馬たちの感動の物語は、DMM TVで全話視聴可能です。
また、原作漫画では、ドラマとは異なる展開や結末が描かれています。ぜひ読み比べてみてください。
ポイント
- 『仁』はペニシリンの登場が物語の核
- 仁の名言は「命を救いたい」という強い意志の表れ
- ペニシリンは仁が青カビと醤油麹から精製
- ペニシリンの登場は第1期第4話から第6話
- ペニシリンは梅毒や細菌感染症に薬効あり
- 夕霧花魁への投与で薬効が証明された
- 「コロリでございます」はコレラを意味する言葉
- 「ペニシリンでございます」はモノマネでも有名
- 綾瀬はるか演じる咲の名言も多い
- 咲の「生きておりますよ」は名セリフ
- 坂本龍馬の名言は日本の未来を思う言葉
- 龍馬の「もっぺん、生まれてきたい国に」が有名
- 史実でペニシリンを国産化したのは昭和の研究者
- 稲垣長治氏らが国産化に貢献した
- 仁の名言とペニシリンは医療の理想を描いている
関連
-

ネットの名言の元ネタと意味!有名ミームを徹底解説
2025/11/11
-

ネガティブな名言で疲れたあなたの心を癒す言葉たち
2025/11/10
-

人生を変えるセリフの名言集:活用術と心に響く言葉たち
2026/1/22
-

贈る言葉の名言を失敗なしで選ぶ極意とマナー!人生の節目で役立つ
2025/11/3
-

名言の面白い言葉に隠された人生の真実とウィットを解説
2025/11/3