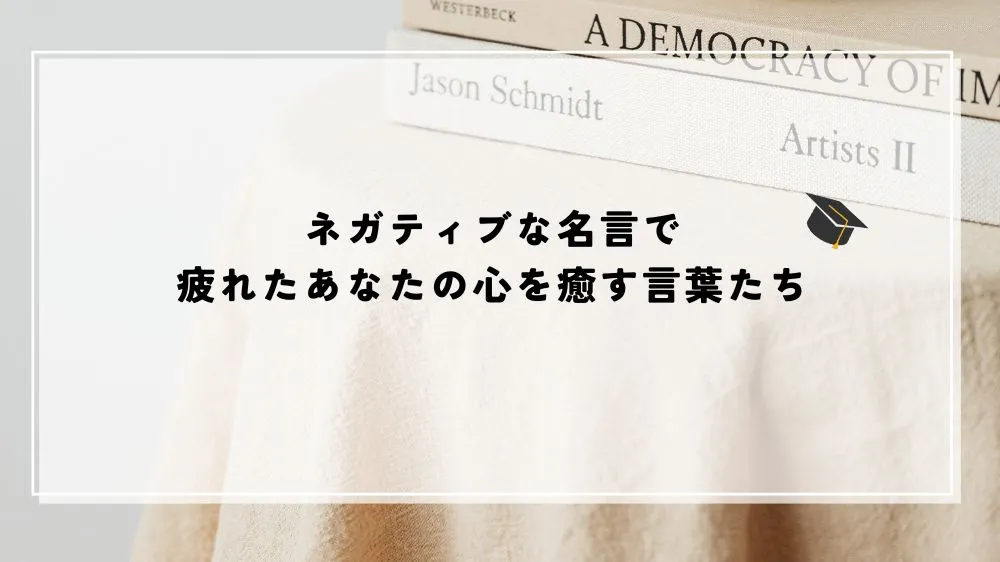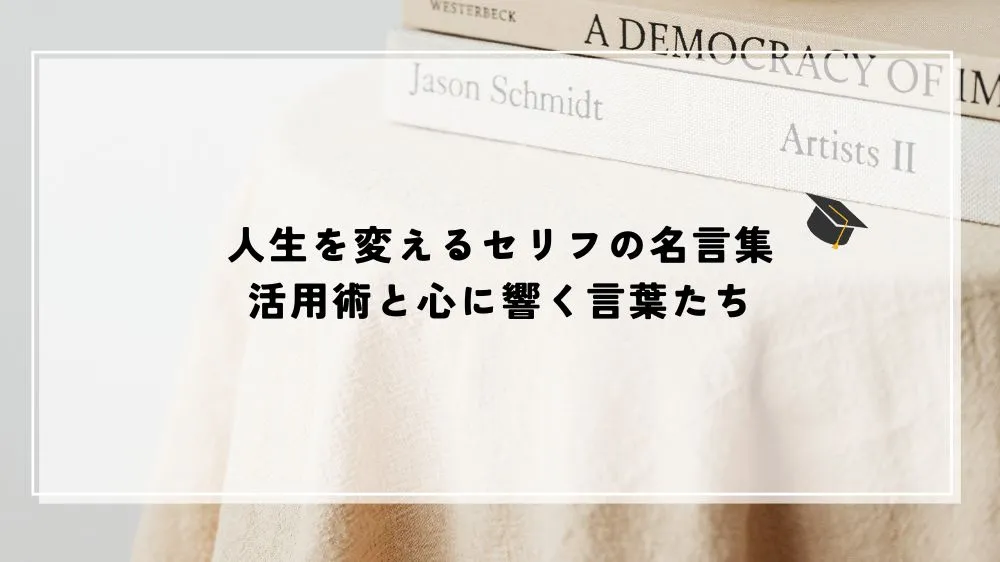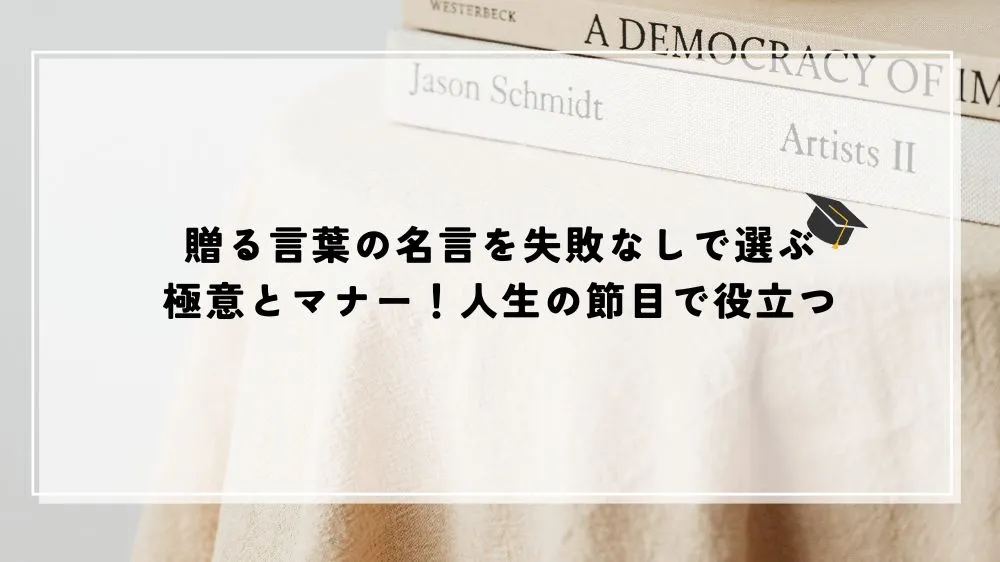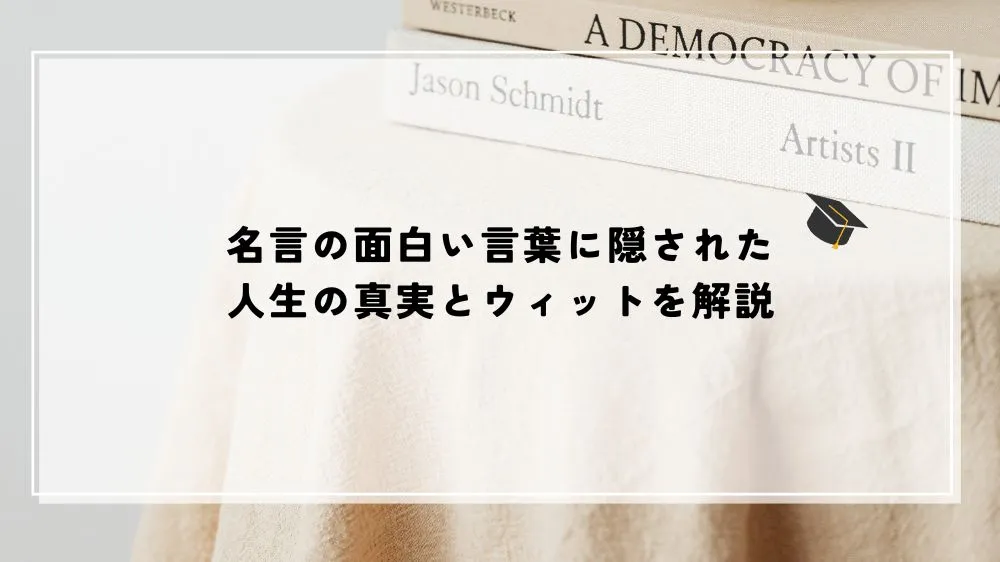短い言葉で心を掴む、キャッチコピーの名言の世界は奥深いものです。私たちは日常で、思わず記憶に残る心に刺さるキャッチコピーや、人を惹きつける キャッチコピー例に数多く触れています。
これらの中には、時代を超えて語り継がれる名作や思わず笑みがこぼれる面白いものも少なくありません。この記事では、具体的なキャッチコピーの例文や有名なキャッチフレーズ一覧を紹介します。
さらに、旅情を誘う行きたくなるキャッチコピー例から、食欲を刺激する美味しそうなキャッチコピーまで、様々な事例を詳細に解説します。優れたコピーを生み出すためのキャッチコピーの考え方やアイディアのヒントも探っていきます。
この記事の内容
- 心に刺さる名言キャッチコピーが持つ力
- 人を惹きつけるキャッチコピーの共通点や事例
- 時代を超えて愛される名作や面白いコピー
- キャッチコピー作成の基本的な考え方とアイディア
人々の記憶に残るキャッチコピーの名言集
ポイント
- キャッチコピーの名言が持つ力とは
- 心に刺さるキャッチコピーの共通点
- 人を惹きつけるキャッチコピー例を紹介
- 時代を超える名作コピー
- ユーモラスで面白いコピー
キャッチコピーの名言が持つ力とは
そもそもキャッチコピーとは、広告や宣伝において、受け手の注意を引きつけるために用いられる短い言葉です。
これは「キャッチ(catch=掴む)」と「コピー(copy=広告文)」を組み合わせた和製英語とされており、その名の通り「読み手の心を掴む言葉」を指します。要するに、「ユーザーの関心を引くための言葉」と言えるでしょう。
しかし、優れたキャッチコピーは、単に商品やサービスを説明するだけにとどまりません。それはまるで名言のように、見た人の心に深く響き、共感を呼び、ブランドのイメージを鮮明に形作ります。
時には消費者の価値観に影響を与え、具体的な行動(購入、訪問、検索など)さえも引き起こす強力な力を持っています。
キャッチコピーは、情報過多の現代社会において、生活者の注意を引きつける「トリガー(引き金)」として機能します。魅力的なコピーであるほど、以下のような多角的な効果が期待できます。
- ブランド認知の向上: 企業名や商品名を強く印象付け、記憶に残りやすくします。「インテル入ってる」のように、フレーズ自体がブランドの代名詞となることもあります。
- イメージ(世界観)の構築: 「楽しそう」「信頼できそう」「革新的だ」といった、ブランドが持つ具体的なイメージや世界観を瞬時に伝達します。
- ターゲットとの共感創出: ターゲット層が潜在的に抱える悩みや願望、価値観に訴えかけることで、「これは自分のための言葉だ」という強い共感を生み出します。
- 行動の促進: 「買いたい」「行ってみたい」「試してみたい」という、消費者の具体的な次の行動を引き出す直接的なきっかけを作ります。
このように、効果的なキャッチコピーは、ブランドと消費者を結びつける、非常に重要かつ戦略的なコミュニケーションの核となる役割を担っているのです。
心に刺さるキャッチコピーの共通点
名作と呼ばれるキャッチコピーや、多くの人々の心に刺Sさるものには、いくつかの普遍的な共通点が存在します。これらは、優れたコピーライティングにおける基本的な技術でもあります。
第一に、短く簡単な言葉で構成されている点です。人は一瞬で多くの情報を処理できません。特に広告は読み飛ばされることが前提です。
そのため、誰もが知っている平易な言葉を使用し、可能な限り簡潔にメッセージを凝縮することで、見た瞬間に意図が伝わり、注目を集めることができます。
第二に、ターゲットが明確であることです。「すべての人」に向けた言葉は、結果として「誰の心」にも響かない平凡なものになりがちです。
誰に伝えたいのか(例:仕事に疲れたビジネスパーソン、子育てに悩む母親、新しい趣味を探す若者)をはっきりと定めることで、その特定の個人の心に「自分ごと」として深く刺Sさる、鋭いメッセージとなります。
インプットした情報の中のゼクシィのコピーは、まさに「結婚を意識し、その意味を考える人」というターゲットに強く響くよう設計されています。他にも、以下のような特徴が挙げられます。
- 共感性: 読者が普段感じている悩み、喜び、願望などに寄り添い、「たしかに」「わかる」と思わせる内容。(例:「がんばるひとの、がんばらない時間。」)
- 意外性(新しい視点): 常識や固定観念を覆すような新しい視点や、常識とは逆の言葉(例:「まずい!もう一杯!」)を用いることで、強い驚きと印象を与えます。
- 好奇心を煽る表現: 「なぜ?」「どういうこと?」と、読み手が思わず続きや詳細を知りたくなるような、問いかけや含みを持たせた表現。
- リズム感(音の心地よさ): 韻を踏んだり(例:「インテル入ってる」)、五七五のような心地よい語呂合わせにしたりすることで、口ずさみやすく、記憶に残りやすくなります。
- 一貫性: 企業や商品のイメージ、ブランドの哲学と、コピーが伝えるメッセージが完全に一致しており、ブレがないこと。
これらの要素が、商品やサービスの「本質的な価値」と組み合わさったとき、単なる言葉が「心に刺Sさる」強力なメッセージへと昇華するのです。
人を惹きつけるキャッチコピー例を紹介
ここでは、特に人を惹きつける力を持ったキャッチコピーの具体例を見ていきましょう。これらは、商品の特徴、利用シーン、または消費者の深層心理を見事に捉えています。
例えば、カルビーの「かっぱえびせん」のコピーとしてあまりにも有名な「やめられない、とまらない」というフレーズ。
これは、カルビー公式サイトの情報によれば、1964年の発売当初からテレビCMなどで使われている息の長いコピーです。(出典:カルビー株式会社「かっぱえびせんヒストリー」)商品の持つ、後を引く美味しさ、食べ始めたら止まらなくなるという「中毒性」とも言える特徴を、これ以上なく的確に表現しています。
多くの人が一度は口ずさんだことがあるほど、商品体験と強く結びついて浸透しました。
また、近年で話題になった例として、Netflixが年末の帰省シーズンに展開した交通広告のコピーがあります。「聞いて驚くな。実家は意外とやることないぞ。」という、少し意地悪くも聞こえる煽るような言葉は秀逸です。
年末年始に帰省する多くの人々(特に若者層)に対し、「たしかにそうだ」「実家は暇だ」という強い共感を呼び起こしました。そして、「その暇な時間に家族みんなでNetflixを」という、自社サービスの利用シーンを強力に印象付けました。

これらのコピーは、消費者の特定の感情(美味しさ、共感、少しの皮肉)や、特定の状況(帰省)に焦点を当て、強い共感や納得感を生み出すことで、人々を強く惹きつけています。
時代を超える名作コピー
キャッチコピーの中には、その時代や世代を超えて多くの人々に愛され続け、もはや社会の共通言語、あるいは文化的なアイコンとさえなっている「名作」が存在します。
その最も有名な例の一つが、JR東海の「そうだ 京都、行こう。」です。1993年から始まったとされるこのキャンペーンは、JR東海「そうだ 京都、行こう。」公式サイトでも確認できるように、25年以上にわたって続いています。
このコピーは、「JR東海の新幹線を使えば、思い立った時にすぐ京都へ行ける」という移動の利便性と手軽さを、「そうだ」という日常的な気づきの言葉で見事に表現しました。
美しい京都の四季の映像と印象的な音楽(「私のお気に入り」)と共に、人々の心に深く刻まれています。
また、ドトールコーヒーの「がんばるひとの、がんばらない時間。」も、多くの人の心に響く名作です。
これは、日々の仕事や勉強で忙しくがんばっている人々が、ほんの少し肩の力を抜き、リラックスできる「止まり木」のような場所と時間を提供する、という企業の姿勢を非常に優しい言葉で表現しています。
情緒的な言葉選びを使い、ブランドが持つ独自のストーリーや世界観を一文に凝縮した例も多くあります。
| 企業・ブランド | キャッチコピー | 伝えたいイメージ・背景 |
| LUMINE | わたしらしくをあたらしく | 都会で働き、常に自分をアップデートし続けたいと願う女性をターゲットに、「LUMINEがその自己実現の場所である」という存在価値を示しています。 |
| カルピス | ピースはここにある。 | ブランド100周年を記念したコピー。「カルピス」のそばにある、家族や友人との健やかでかけがえのない時間や場所こそが「平和(ピース)」である、というメッセージを伝えています。 |
これらの名作コピーは、単に商品を売るためだけでなく、ブランドの哲学や社会的な存在意義を伝え、消費者との長期的な関係を築くことに成功しています。
ユーモラスで面白いコピー
思わず「ふふっ」と笑ってしまったり、その機転の利いた遊び心に感心したりするユーモラスなキャッチコピーも、人々の記憶に強く残る手法の一つです。
その代表的な例が、有楽製菓「ブラックサンダー」がバレンタイン商戦で用いた「一目で義理とわかるチョコ」です。日本のバレンタインデーには、本命チョコだけでなく「義理チョコ」という独特の文化が存在します。
このコピーは、その事実を逆手に取り、高価な本命チョコとは一線を画す、義理チョコとして最適なブラックサンダーのカジュアルさ(手頃な価格、気兼ねのなさ)を、見事に、そしてユーモラスに表現しました。
このキャンペーンは大きな話題となり、ブラックサンダーの売上増にも貢献したと言われています。(参考:ブラックサンダー公式サイト)
「面白い」ことの難しさとリスク
ユーモアは、ターゲット層の価値観、文化的背景、あるいは時代性によっては、意図せず誰かを傷つけたり、不快にさせたりするリスクも伴います。いわゆる「炎上」につながる可能性もゼロではありません。
しかし、ブラックサンダーの例のように、ブランドの立ち位置(キャラクター)と、ターゲット層のインサイト(義理チョコ選びの面倒くささ)、そして社会的な文脈(バレンタイン文化)が完璧に合致した場合、それは非常に強力な共感を生み出し、SNSなどを通じて爆発的に拡散されるポジティブな力となります。
前述のNetflix「聞いて驚くな。実家は意外とやることないぞ。」も、このユーモアと共感を両立させた好例です。少し意地悪くも聞こえる「煽り」が、逆に「図星だ」「よく言ってくれた」というターゲットの笑いを誘い、サービス利用へと巧みにつなげています。
これらのコピーは、洗練されたジョークや、あえて本音を突くような遊び心を通じて、商品やサービスのユニークな立ち位置を強調することに成功しているのです。
参考になるキャッチコピー 名言の型
ポイント
- 参考になるキャッチコピー 例文
- 有名なキャッチフレーズ 一覧
- 行きたくなるキャッチコピー例
- 美味しそうなキャッチコピーの世界
- キャッチコピー 考え方とアイディア
- キャッチコピー 名言からヒントを得よう
参考になるキャッチコピー 例文
ここでは、商品やサービスの魅力、あるいは企業の社会的な姿勢を、上手に、そして印象的に伝えている、参考になるキャッチコピーの例文をいくつか深掘りして紹介します。
リクルートが発行する結婚情報誌「ゼクシィ」の「結婚しなくても幸せになれるこの時代に、私は、あなたと結婚したいのです。」は、2017年に発表され、社会現象とも言えるほど大きな話題となりました。
このコピーが秀逸なのは、「結婚=幸せ」という旧来の画一的なステレオタイプをまず否定し、多様な生き方(結婚しない選択)も尊重する現代の価値観に寄り添っている点です。
その上で、「それでもなお、私は“あなたと”結婚することを選ぶ」という、個人の強い意志と決意を描き出しました。これにより、結婚の多様化が進む現代において、改めて結婚の意味を問う多くの人々の共感を呼びました。
また、商品の機能的な価値(ベネフィット)を端的に伝えた例として、ニトリの「お、ねだん以上。」があります。CMでお馴染みのこのコピーは、「お!」という驚きや発見を示す会話調の表現を用いることで、消費者に親しみやすさを感じさせます。
そして「値段以上」という言葉で、単なる安さ(価格)ではなく、それ以上の価値(品質やデザイン)を提供しているという、企業のコストパフォーマンスの高さを一言で、かつ強力に表現しています。
| その他の秀逸な例文とそのポイント | ||
| 企業・ブランド | キャッチコピー | ポイント解説 |
| 明治 R-1 | これからの地球のために一肌、脱ぎました。 | 商品のリニューアル(ラベルレス化)という環境配慮の取り組みを、「一肌脱ぐ」という慣用句で表現したコピーライティングの妙。 |
| POCARI SWEAT | 自分は、きっと想像以上だ。 | 従来の「水分補給」という機能訴求から転換し、部活や学園祭など、何かに打ち込む若者のポジティブなエネルギーと自己超越の可能性を刺激しています。 |
| ハーゲンダッツ | ハローしあわせ。 | 「ご褒美アイス」としての立ち位置を確立。商品を食べた時の「ちょっとした幸せな感情(エモーショナルベネフィット)」を「ハロー」という挨拶で擬人化し、表現しています。 |
| Suica | 日本を、1枚で。 | 当初は首都圏限定だったSuicaが全国相互利用可能になったことの利便性の高さを、「日本を」「1枚で」という圧倒的なスケール感と簡潔さで伝えています。 |
| PILOT | 言えないことの方が多いから、人は書くのだと思う。 | デジタル化が進む現代において、「書く」という行為が持つ情緒的な価値(言葉にできない想いを伝える手段)に寄り添い、筆記具の存在意義を再定義しています。 |
| サッポロビール | 乾杯をもっとおいしく。 | あえて「ビール」という商品名を出さず、「乾杯」という楽しい飲酒シーンそのものを主語にすることで、そのシーンに欠かせない存在として自社製品を想起させます。 |
これらの例文からわかるように、優れたコピーは何を伝えたいのか(機能、感情、姿勢、利便性)を徹底的に明確にし、それをターゲットに最も響く的確な言葉に落とし込んでいることが分かります。
有名なキャッチフレーズ 一覧
企業名やブランド名と強く結びつき、多くの人々に広く認知されている有名なキャッチフレーズも多数存在します。中には、企業名を巧みに織り込んだものや、国境を越えてグローバルに展開されているスローガンもあります。
企業名に絡めたキャッチコピー
企業名やサービス名をうまく利用したコピーは、リズム感が良く、ブランド名自体を消費者の記憶に残りやすくする効果があります。
・マイペースに、マイペアーズ (Pairs)
マッチングアプリ「Pairs(ペアーズ)」のコピーです。「マイペース」とサービス名「ペアーズ」を巧みに掛け合わせて(韻を踏んで)います。急かされることなく、自分らしいペースで恋愛や出会いを見つけられる、というサービスの価値を分かりやすく伝えています。
・どうする?GOする! (GO株式会社)
タクシー配車アプリ「GO」のコピーです。「終電を逃した、どうしよう」「雨が降ってきた、どうしよう」といった、タクシーが必要になる「どうする?」という困ったシチュエーションと、「GOする!」というアプリを使った解決行動を、対比させながらリズミカルに表現しています。
・インテル入ってる (Intel)
パソコンのCPUメーカー「Intel(インテル)」のコピーです。「インテル」と「入ってる」で「てる」の音で韻を踏むことで、非常に耳に残りやすいフレーズとなっています。
多くのパソコンに自社製品が搭載されているという事実(普及率)と、それによる安心感・信頼感をアピールしました。CMの最後に流れる特徴的なサウンドロゴと共に、世界的に有名になりました。
英語のキャッチコピー
国境を越えて共感を呼び、ブランドの哲学そのものをグローバルに届ける英語のキャッチコピー(スローガン)も有名です。
| 企業・ブランド | キャッチコピー | 伝えたいイメージ・背景 |
| Nike | Just Do It. | 「とにかくやってみろ」「行動あるのみ」という意味が込められた、ナイキのブランド哲学そのものを表すスローガンです。スポーツ選手だけでなく、何か新しいことに挑戦しようとするすべての人々の背中を押す、強力なメッセージとなっています。 |
| タワーレコード | NO MUSIC, NO LIFE. | 「音楽がなければ、人生じゃない」「音楽なしの人生なんてありえない」という、音楽への深い愛情とリスペクトを表現した企業メッセージです。時代を超えて、音楽を愛するすべての人の心を掴み続けています。 |
行きたくなるキャッチコピー例
旅行業界、観光地、あるいはテーマパークなどでは、人々の「そこへ行ってみたい」「体験してみたい」という欲求や好奇心を強く刺激するキャッチコピーが非常に重要な役割を果たします。
その代表例として、何度も登場しますが、やはりJR東海の「そうだ 京都、行こう。」は外せません。このコピーが特に秀逸なのは、「旅行喚起」の側面に特化している点です。
美しい京都の寺社仏閣の映像と、CMで使われる印象的な音楽(『サウンド・オブ・ミュージック』の「私のお気に入り」)との完璧な相乗効果により、「今度の休み、ふらっと京都に行ってみようか」という具体的な行動喚起に直結しています。
また、2022年に開業したジブリパークが使用した「ゆっくりきてください」というコピーも非常に印象的です。これは、一般的なテーマパークが「早く来て!」「さあ楽しもう!」と高揚感を煽るのとは全く対照的です。
ジブリ作品の持つゆったりとした世界観と、「パーク内は混雑も予想されるため、慌てず、ご自身のペースでゆっくりと楽しんでほしい」という来園者への配慮やメッセージが込められており、ファンの期待感をジブリらしく高めました。
世界観(体験価値)を伝えるコピー
「行きたくなる」コピーは、場所そのものだけでなく、そこで得られる「体験価値」を伝えることが重要です。その好例が、三鷹の森ジブリ美術館の「迷子になろうよ、いっしょに。」というコピーです。
このコピーは、一般的な美術館と異なり、あえて順路を設けていないという施設の構造的な特徴と、「効率よく展示を見て回るのではなく、迷いながら自分だけの発見をする楽しみを体験してほしい」という、施設が提供する思想(体験価値)を見事に表現しています。これにより、訪問前から「どんな場所なんだろう」というワクワク感を掻き立てます。
これらのコピーは、単に場所の物理的な魅力を伝えるだけでなく、そこで過ごす「時間」や「体験」、そしてその場所が持つ「世界観」を豊かに想像させ、訪問意欲を強く刺激します。
美味しそうなキャッチコピーの世界
食品や飲料、飲食店の分野では、人間の五感、特に味覚や嗅覚に訴えかけ、「美味しそう」「食べてみたい」と直感的に感じさせるキャッチコピーが求められます。
前述の「やめられない、とまらない」(かっぱえびせん)や「ハローしあわせ。」(ハーゲンダッツ)は、実際に食べた時の感覚(後引く旨味)や、食べた後に訪れる幸福感(感情)を表現した優れた例です。
また、「乾杯をもっとおいしく。」(サッポロビール)は、「乾杯」というビールが最も美味しく感じられるシーンと、商品の美味しさを巧みに結びつけました。
より直接的に味や食感を表現したり、好奇心を刺激したりするコピーもあります。

どうやらうまいらしい(栗山米菓 瀬戸しお)
あえて「うまい!」と断定せず、「~らしい」という噂や伝聞の形を取ることで、「本当か?」「どれほど美味しいのか?」という読み手の好奇心を刺激し、試してみたいという欲求を喚起します。
ニュー! ベリー! ハッピー!!(有楽製菓 ミルクないちごのサンダー)
「NEW(新しい)」と「乳(ミルク)」、「VERY(とても)」と「BERRY(いちご)」をリズミカルに掛け合わせる(ダブルミーニング)ことで、新商品の楽しさ、いちごミルクの美味しさ、そして食べた時のハッピーな気分を表現しています。
自然のおいしさと。 人の想うおいしさと。(シャトレーゼ)
「自然のおいしさ(=素材へのこだわり)」と「人の想うおいしさ(=顧客のニーズに応える姿勢)」の両方を並べることで、美味しさへの多角的なアプローチと、食への安心感を伝えています。
明太子をつくってよかった。(ふくや)
創業者が初めて明太子を作った時の万感の想いが込められたような、非常にストレートでエモーショナルな言葉です。この作り手の純粋な喜びが、製品への絶対的な自信と「きっと美味しいに違いない」という期待感を消費者に伝えます。
キャッチコピー 考え方とアイディア
では、実際に人々の心に響くキャッチコピーを作成する際、どのような考え方やアイディアの出し方があるのでしょうか。インプットした情報(主に採用キャッチコピーの作り方)も参考にしつつ、一般的な作成プロセスと発想のテクニックを解説します。
優れたキャッチコピーは、単なる天からの「閃き」だけでは生まれません。ターゲットのインサイト(深層心理)を深く理解し、伝えるべきメッセージを研ぎ澄ます、論理的なステップに基づいた思考が不可欠です。
キャッチコピー作成の基本4ステップ
どのようなキャッチコピーを作る上でも、以下の4つのステップは基本となります。
- ターゲットの明確化(誰に)まず、「誰に」伝えたいのかを徹底的に明確にします。年齢や性別といったデモグラフィック情報だけでなく、その人が日常で何に悩み、何を喜び、どのような価値観を持っているかといった「ペルソナ(具体的な人物像)」まで設定します。
- 自社(商品)の魅力の抽出(何を)次に、ターゲットに対して「何を」伝えるかを整理します。商品やサービスが持つ特徴(機能、価格、デザインなど)や利点(ベネフィット=それによって得られる良い未来)を全て書き出します。特に、他社にはない優位点(差別化ポイント)は何かを明確にします。
- コンセプトの決定(どう)「誰に」「何を」伝えるかが決まったら、「どう」伝えるかというコンセプト(切り口)を決定します。数ある魅力の中から、設定したターゲットに最も響くであろう魅力(例:「手軽さ」なのか「高級感」なのか「共感」なのか)を一つ選び出し、コピーの核となるメッセージを定めます。
- フレーズ作成(言葉にする)最後に、定めたコンセプトをターゲットに伝わる具体的な「言葉」に落とし込みます。この段階で、様々な表現テクニックを用います。
フレーズ作成のテクニック(アイディア発想法)
フレーズを作成する際には、以下のようなテクニック(切り口)が役立ちます。
- 数字を使う: 「100人乗っても大丈夫!」「10秒チャージ」「3,900万人の働き方を変える」のように、具体的な数字を入れることで、メッセージの具体性、説得力、インパクトが格段に増します。
- 利点(ベネフィット)を示す: ターゲットがその商品やサービスから得られる「理想の未来」を具体的に示します。(例:「未経験からプロへ」「世界の料理を食べ尽くそう!」)
- キャッチーな表現(音): 疑問形(どうする?)、命令形(Just Do It.)、呼びかけ(聞いて驚くな。)、擬音語、韻を踏む(インテル入ってる)など、音として記憶に残りやすい言葉を選びます。
- 意外性(逆説)を持たせる: 常識とは逆のこと(まずい!もう一杯!)や、一見矛盾する言葉(結婚しなくても幸せになれるこの時代に、結婚したい)をあえて使うことで、強いフック(引っかかり)を作り、読者の関心を引きます。
注意点:奇抜さだけを追わない
キャッチーな表現や意外性を意識するあまり、奇抜さだけを重視してしまうと、本来伝えたかった魅力や企業イメージと乖離(かいり)してしまう危険性があります。
また、誇張が過ぎる表現は、消費者に誤解を与える可能性もあります。消費者庁が定める景品表示法などでも、消費者に誤解を与えない「分かりやすい表示」が求められています。(参考:消費者庁「景品表示法」)
必ず「ターゲット」に「伝えるべき魅力(ベネフィット)」が「正しく」伝わるかという原点に立ち返り、複数の案を比較検討することが非常に大切です。
キャッチコピー 名言からヒントを得よう
この記事では、様々な名作キャッチコピーを、その背景や効果と共に深掘りしてきました。最後に、優れたキャッチコピーから私たちが得られるヒントを、要点としてまとめます。
ポイント
- キャッチコピーは商品やサービスの注意を引くための短い言葉
- 名言のように人の心を動かしブランド認知を高める力を持つ
- 心に刺Sさるコピーは短く簡単でターゲットが明確である
- 共感性や意外性、そして心地よいリズム感も重要な共通点
- 「やめられない、とまらない」は商品の本質的な特徴(中毒性)を的確に表現
- 「そうだ 京都、行こう。」は利便性と情緒に訴え行動を喚起した名作
- 「一目で義理とわかるチョコ」はユーモアで商品の独自の立ち位置を確立
- 「結婚しなくても幸せになれるこの時代に」は現代の価値観に寄り添い深い共感を呼んだ
- 「お、ねだん以上。」は価格以上の価値(ベネフィット)を会話調で伝えている
- 企業名と韻を踏む(インテル入ってる)手法はブランド名の記憶に効果的
- 「NO MUSIC, NO LIFE.」はブランドの哲学と顧客の情熱を代弁
- 「迷子になろうよ、いっしょに。」は施設の思想とユニークな体験価値を表現
- 「どうやらうまいらしい」はあえて断定せず好奇心を刺激する高等テクニック
- 優れたコピー作成は「誰に」「何を」「どう伝えるか」の論理的なステップから生まれる
- コピー作成はターゲットの明確化から始まる
- 魅力の抽出、コンセプト決定を経て具体的なフレーズを作成する
- 数字の使用、利点の提示、逆説などはフレーズ作成の有効なテクニック
- 惹かれるコピーに出会ったら「なぜ心が動いたのか」を分析することがヒントになる
関連
-
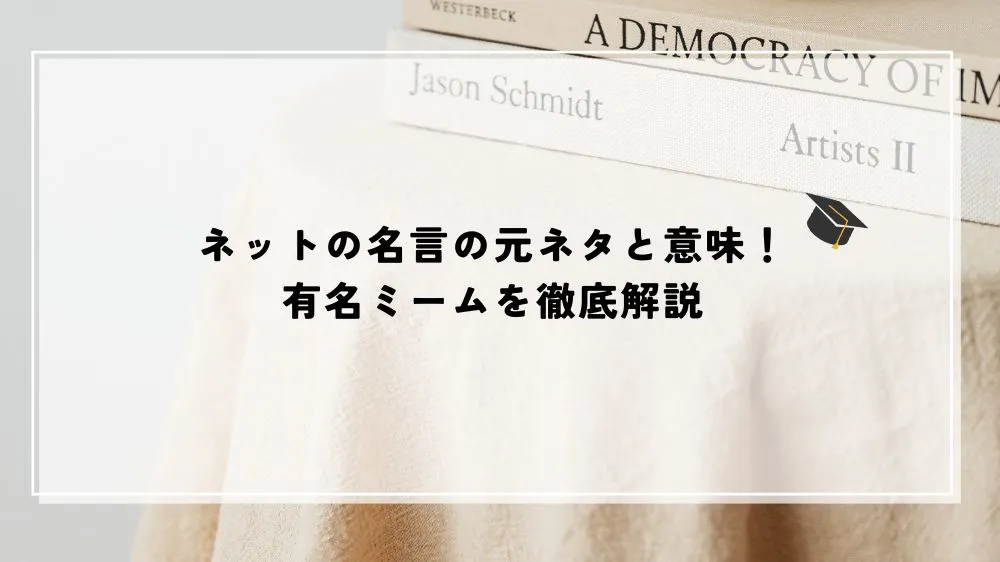
ネットの名言の元ネタと意味!有名ミームを徹底解説
2025/11/11
-

ネガティブな名言で疲れたあなたの心を癒す言葉たち
2025/11/10
-

人生を変えるセリフの名言集:活用術と心に響く言葉たち
2026/1/22
-

贈る言葉の名言を失敗なしで選ぶ極意とマナー!人生の節目で役立つ
2025/11/3
-

名言の面白い言葉に隠された人生の真実とウィットを解説
2025/11/3