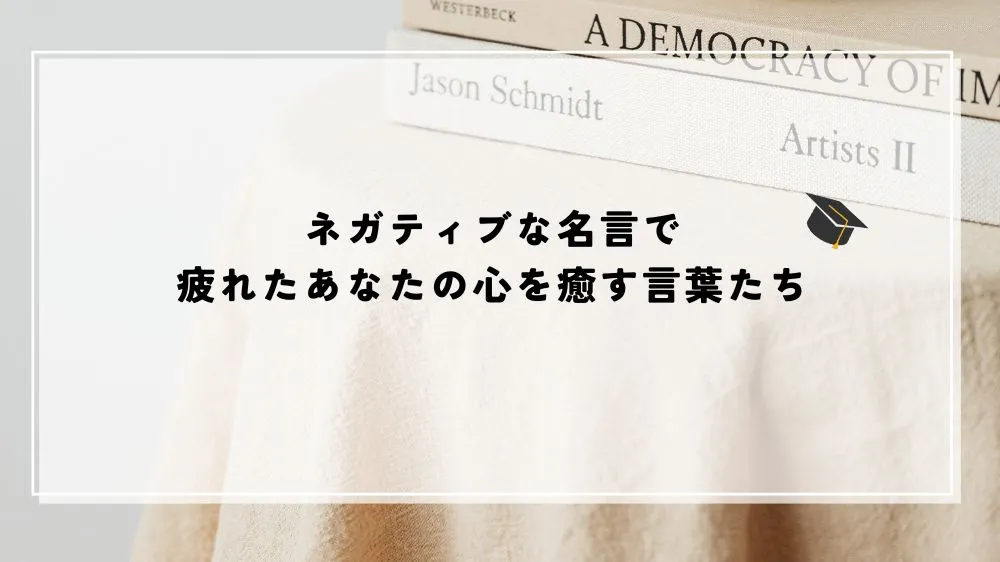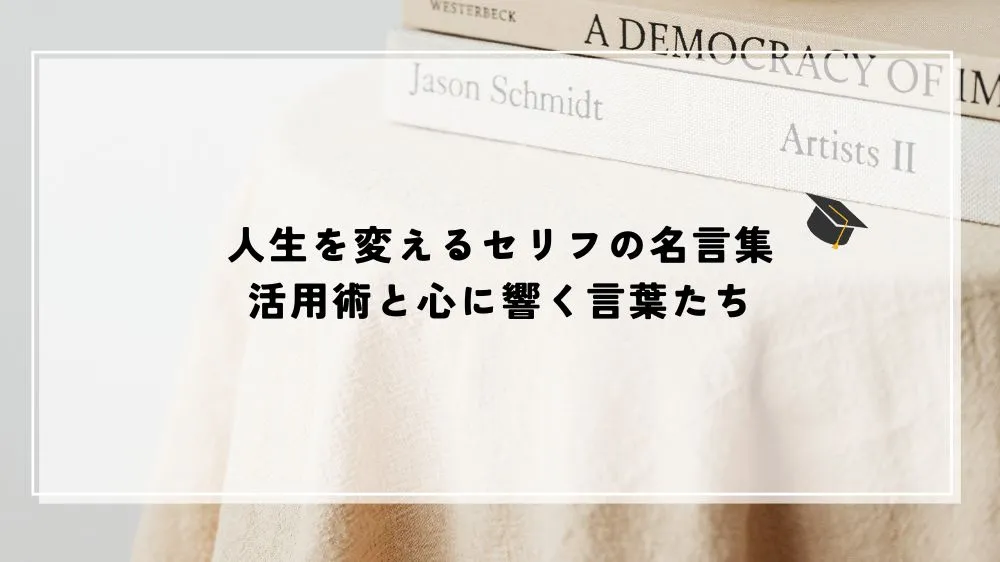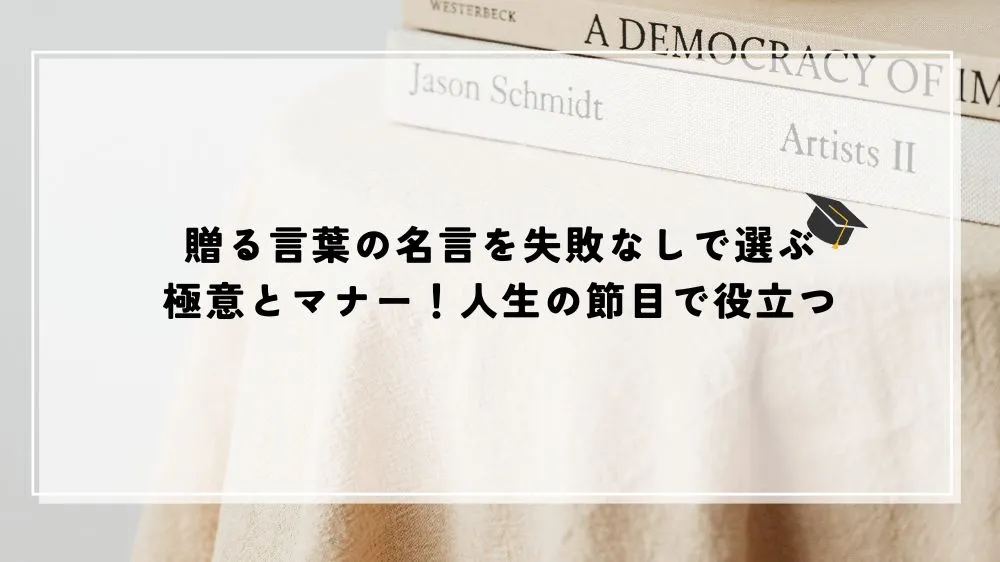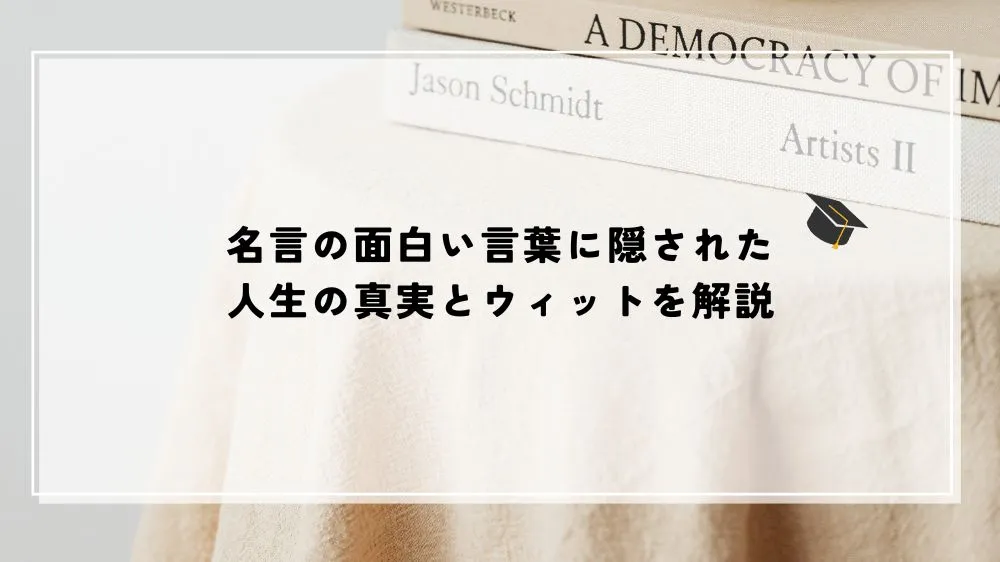「段取り8割」という言葉を見聞きしたことはありますか?仕事は段取り8割が重要とされますが、この段取り八分仕事二分という格言について、仕事は段取りが8割というのはどういう意味ですか?と疑問に思う方もいるでしょう。
また、段取り八分は誰の言葉なのか、その由来や正しい読み方も気になります。この記事では、段取り8割の名言の意味やトヨタの実践例、準備8割を貫いたイチローのエピソード、スピーチで使える例文まで詳しく解説します。
さらに、段取りに関することわざや8割のことわざは?といった疑問にも答え、類語や言い換え表現も紹介します。
この記事の内容
- 段取り 8 割 名言の正確な意味と由来
- トヨタやイチローなど具体的な実践例
- 関連することわざや言い換え表現
- ビジネススピーチで使える例文
「段取り8割の名言」の基本
ポイント
- 段取り八分仕事二分の意味
- 段取り八分の正しい読み方
- 段取り八分は誰の言葉?
- 段取りの由来と語源
- 仕事は段取り8割が重要
段取り八分仕事二分の意味
「段取り八分、仕事二分(だんどりはちぶ、しごとにぶ)」とは、仕事の成果は、実行前の「段取り」で8割が決まるという意味の格言です。
実際の作業(仕事)にかかる割合は2割程度に過ぎず、いかに事前の準備や計画が重要であるかを説いています。これは、文字通り「準備に全時間の8割を費やせ」という意味ではありません。
むしろ、仕事全体の質と効率を追求し、準備の質を徹底的に高めることが本質です。良質な段取りができていれば、実際の作業は驚くほどスムーズに進み、結果的に短時間で質の高い成果が出せるという、仕事の核心を示しています。
この格言における「段取り」とは、具体的に以下のようなプロセスを指します。
「段取り」に含まれる主要な活動
- 目的の明確化:その仕事で何を達成するのか、ゴールをはっきりさせる。
- タスクの分解:ゴール達成に必要な作業をすべて洗い出す。
- 優先順位付け:タスクの重要度や緊急度を判断し、取り組む順番を決める。
- スケジューリング:各タスクの所要時間を見積もり、全体のスケジュールを組む。
- リソース確保:必要な人員、予算、情報、ツールなどを事前に確保する。
- リスクの想定:起こりうる問題や障害を予測し、対策を考えておく。
もし計画が不十分なまま作業を始めると、途中で必要なものが足りないことに気づいたり、予期せぬトラブルに見舞われたりして、作業が中断します。
その結果、手戻り(やり直し)が発生し、かえって多くの時間と労力を浪費してしまいます。この格言は、そうした無駄を徹底的に排除し、効率的に成果を出すための実践的な知恵と言えるでしょう。
段取り八分の正しい読み方
「段取り八分」の正しい読み方は、「だんどり はちぶ」です。
ここで使われる「八分(はちぶ)」とは、割合を示す言葉です。「十分(じゅうぶ)の八」、つまり全体の8割のことを指します。私たちは日常的に「腹八分目(はらはちぶんめ)」という言葉を使いますが、これと同じ用法で、「ほぼ完成に近い状態」や「大部分」を示す表現です。
このため、「段取り八分」は「段取りが8割方終わっていれば(=仕事の勝負はほぼ決まっている)」という意味合いで使われます。ちなみに、続く「仕事二分」は「しごと にぶ」と読みます。
読み方の注意点
「八分」を「はっぷん」と読んでしまうと、時間(8分間)という意味になってしまい、格言本来の「割合」を示す意味とは全く異なってしまいます。格言として引用する際は、「だんどり はちぶ」と正しく読むよう注意が必要です。
段取り八分は誰の言葉?
「段取り八分」は、特定の有名人や歴史上の人物が残した言葉ではありません。
これは、主に日本の建築現場、製造業、料理の世界など、職人たちの仕事場で、古くから経験則として語り継がれてきた「現場の知恵」とも言える格言です。
なぜこれらの現場で特に重視されたかというと、そこでの作業は「品質・コスト・納期・安全」に直結するからです。例えば、建築現場で段取りが悪ければ、資材の搬入が遅れて工期が延びたり、作業手順の連携ミスで重大な事故につながったりします。
製造業でも、段取りの不備は不良品の発生やラインの停止に直結します。
一度のミスが大きな損失につながる厳しい世界だからこそ、実行前の準備がいかに重要かを、先人たちが経験から学び、この言葉に集約したのです。
誰の言葉か特定できない匿名の名言でありながら、その普遍的な真理は多くのビジネスパーソンや経営者にも共感され、引用されています。
例えば、京セラ創業者の稲盛和夫氏やホンダ創業者の本田宗一郎氏といった名経営者も、著書や講演で準備や計画の重要性について繰り返し説いており、この格言に通じる考え方を持っていたことが知られています。
段取りの由来と語源
「段取り」という言葉自体の由来にも、準備の重要性が色濃く表れています。
由来には諸説ありますが、代表的なものとして以下の2つが挙げられます。
1. 歌舞伎の構成に由来する説
最も有力とされる説の一つが、歌舞伎の世界に由来するものです。歌舞伎の脚本や構成において、物語の大きな区切りや一幕を「段(だん)」と呼びます。
そして、その「段」の構成や流れ(取り方)、つまり場面転換のタイミング、役者の出入り、大道具や小道具の配置などを計画することを「段取り」と呼んだという説です。
観客を魅了する舞台を作り上げるためには、役者の本番の演技力だけでなく、これらすべてがスムーズに連携するよう事前の計画を練り上げることが極めて重要です。この緻密な事前計画が、そのまま「段取り」という言葉になったとされています。
2. 石段作りに由来する説
もう一つは、建築現場、特に石段を作る職人の言葉に由来するという説です。坂道に石段を作る際、職人が全体の傾斜の角度や利用者の平均的な歩幅を考慮し、「どのような大きさの石を、何段にわたって、どの高さで配置するか」を詳細に計画しました。
この作業を「段を取る」と表現したと言われます。
適切な計画(段取り)なしに、やみくもに石を積み始めても、安全で歩きやすい階段は決して完成しません。全体の設計図を描き、最適な石を選び、配置を決めるという、まさに事前の計画作業が「段取り」の語源になったという説です。
どちらの説も、最終的な成果物(舞台や石段)の品質は、実行前の設計や準備で決まるという点で共通しており、「段取り八分」の精神そのものを示しています。
仕事は段取り8割が重要
「仕事は段取り8割」と言われる理由は、段取り力が仕事の効率と品質、さらにはコストや安全性にまで直結するからです。
段取りが不十分なまま仕事を進めると、以下のような多くの問題、つまり「ムダ」を引き起こす可能性があります。
段取り不足が引き起こす典型的な「ムダ」
- 手戻りのムダ:途中でミスや漏れが発覚し、前の工程に戻ってやり直す。
- 停滞のムダ:必要な情報やツールが揃っておらず、作業が止まってしまう。
- 重複作業のムダ:連携不足で、他の人がすでに終えた作業を繰り返してしまう。
- 品質低下のリスク:納期に追われ、焦って作業することでミスが増え、成果物の質が下がる。
- コスト増加のリスク:無駄な残業時間が発生し、人件費が増加する。
逆に言えば、しっかりとした段取りを行うことで、これらの問題を未然に防ぐことができます。厚生労働省が推進する「働き方改革」においても、業務効率化や生産性向上のためには、まず「業務の見える化」と「業務フローの見直し」が重要とされています。(出典:厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」)
これはまさに段取りのプロセスそのものです。仕事を始める前に「目的の明確化」「タスクの洗い出し」「優先順位付け」「スケジュール作成」「リスクの想定」といった段取りを済ませておけば、作業者は迷うことなく目の前の業務に集中できます。
これにより、作業スピードと品質が向上し、安定した成果を生み出せるのです。
段取り8割 名言と実践例
ポイント
- 「段取り」の言い換え表現
- 関連することわざを紹介
- トヨタが実践する段取り
- 準備8割を貫いたイチロー
- スピーチで使える例文
- 段取り 8 割 名言の総括
「段取り」の言い換え表現
「段取り」は非常に便利な言葉ですが、ビジネスシーンや日常生活において、文脈に応じて様々な言葉で言い換えることができます。適切な言葉を選ぶことで、より意図が伝わりやすくなります。
「段取り」の主な言い換え表現とニュアンス
- 手順(てじゅん):物事を行う順序やプロセスを指す場合に適しています。「作業の手順を確認する」といった使われ方をし、マニュアル化された流れを指すことが多いです。
- 手続き(てつづき):主に事務的な処理や、決められた形式・規則に沿って事を進める順序を指します。「契約の手続きを進める」「役所への申請手続き」など、公的なニュアンスで使われます。
- 手はず(てはず):事を実行するための準備や計画、順序を指します。「出発の手はずを整える」「関係各所への手はずは済ませた」といったように、特に関係者との調整や根回しを含めた準備全般を意味するニュアンスが強いです。
- 計画(けいかく):将来行うべきことを、目的や順序、方法などを具体的に決めること。「プロジェクトの計画を立てる」など、全体像を描く際に使われます。
- 準備(じゅんび):必要なものを揃えたり、体制を整えたりすること。「会議の準備をする」など、モノや環境を整える物理的な行動を指すことが多いです。
これらの言葉は似ていますが、「段取り」は単なる順序(手順)や机上の計画だけでなく、それを実行するための具体的な準備(手はず)や関係者との調整までを含む、より広範で実践的な概念として使われることが多いのが特徴です。
関連することわざを紹介
「段取り八分」のように、準備の重要性を説く名言やことわざは、時代や国境を越えて数多く存在します。これは、準備の重要性が普遍的な真理であることを示しています。
これらを知っておくことで、段取りの重要性について多角的に理解を深めることができます。
| 名言・ことわざ | 提唱者・出典 | 意味・解説 |
| 勝敗は戦う前に決まっている | 孫子(古代中国の兵法書) | 実際の戦闘(実行)が始まる前の、綿密な情報収集、計略、準備(算段)こそが勝利を決定づけるという意味。 |
| If I had six hours to chop down a tree, I'd spend the first four sharpening the axe. (木を切る時間が6時間与えられたら、斧を研ぐのに4時間使うだろう) | エイブラハム・リンカーン(米国大統領) | 実行(木を切る)そのものよりも、道具の準備(斧を研ぐ)という段取りにこそ、多くの時間をかける重要性を示しています。 |
| 備えあれば憂いなし | 書経(中国の古典) | 日頃から準備を怠らなければ、万が一の緊急事態(憂い)が起きても、心配することはないという意味。 |
| 転ばぬ先の杖 | 日本のことわざ | 転んで怪我をしないように、あらかじめ杖を用意しておくこと。失敗しないように、事前に用心して準備を整えておくことのたとえ。 |
このように、西洋の経営者(リンカーン)から東洋の兵法家(孫子)まで、一流の成果を出した人物は皆、実行そのものよりも「準備」の段階を最重要視していたことが分かります。

トヨタが実践する段取り
「段取り八分」を企業文化として徹底的に実践し、世界レベルの生産性を実現している代表例が、トヨタ自動車です。
同社の強さの源泉である「トヨタ生産方式(TPS)」において、「段取り替え」は非常に重要なプロセスと位置づけられています。
トヨタ式の「段取り」とは
製造業における「段取り替え」とは、一つの製品(例:A部品)の生産が終了した後、次に異なる製品(例:B部品)を作るために、プレスマシンなどの機械の金型や治具(じぐ)を交換・調整する準備作業を指します。
かつて、この段取り替え作業には数時間かかるのが当たり前でした。
ラインが止まっている間は製品を生み出せないため、多くの企業はこの時間を「非効率なロスタイム」と捉え、一度の生産で大量に作る(大ロット生産)ことで段取り替えの回数を減らそうとしました。
しかし、これは大量の在庫を生む原因にもなります。
一方、トヨタは逆の発想を持ちました。「段取り替えの時間を極限まで短縮すれば、必要なものを必要なだけ(小ロットで)作れる」と考えたのです。
トヨタは「カイゼン」を重ね、数時間かかっていた作業を10分未満(シングル段取り)に短縮することに成功しました。これは、徹底した準備(段取り)がなければ不可能です。
例えば、交換用の金型を事前に温めておく、ボルトをワンタッチで固定できる治具を開発するなど、すべて「実行(交換作業)を最短にするための準備」でした。
この革新により、多品種少量生産を効率的に行い、「ジャストインタイム」(必要なものを、必要な時に、必要なだけ作る)というトヨタ生産方式の根幹が実現しました。(出典:トヨタ自動車株式会社「トヨタ生産方式」)
トヨタにとって段取りとは、単なる準備作業ではなく、無駄をなくし、生産性を高め、さらには企業の競争力(在庫削減と顧客ニーズへの即応)までをも高めるための「最も重要な仕事」なのです。
準備8割を貫いたイチロー
元メジャーリーガーのイチロー氏もまた、「準備8割」の重要性を誰よりも深く理解し、体現した人物の一人です。
彼は、試合で最高のパフォーマンスを発揮するために、常人には真似できないほどの徹底した準備を、日々の厳格なルーティンとしていました。
試合当日の朝にカレーを食べること(後に否定されましたが、ルーティンの象徴として有名)はもちろん、試合前の入念なストレッチ、緻密な食事管理、バットやグローブといった道具の徹底した手入れ、トレーニング、睡眠時間の確保に至るまで、すべてが「試合で結果を出す」という一点に向けた準備(段取り)でした。
イチロー氏にとって、本番の試合は「自分がしてきた準備が正しかったかどうかを確認する作業」に過ぎなかったとも言われています。彼は、準備について次のような名言を残しています。
「準備というのは、言い訳の材料を排除していく作業です」
この言葉の意味は、試合で結果が出なかった時に、「あの準備が足りなかったからだ」「道具のせいだ」といった言い訳を一切作らないために、考えうる全ての準備を完璧に行う、ということです。
また、彼は道具の手入れを欠かさないことで、バットのわずかな重心の変化やグローブの微妙な歪みにも気づくことができました。
彼にとって準備とは、単なるルーティンであると同時に、自身のコンディションや環境の微細な変化を察知するための「センサー」でもあったのです。
イチロー氏のこの姿勢と哲学は、「段取り八分、仕事二分」の精神を最も高いレベルで実践した証と言えるでしょう。
スピーチで使える例文
「段取り八分、仕事二分」は、その意味の深さと分かりやすさから、朝礼や会議など、ビジネスシーンのスピーチでも活用しやすい格言です。
この言葉を使って、チームの意識を統一したり、プロジェクトへの取り組み方を確認したりすることができます。
スピーチで使える例文
「段取り八分、仕事二分」は、その意味の深さと分かりやすさから、朝礼や会議など、ビジネスシーンのスピーチでも活用しやすい格言です。
この言葉を使って、チームの意識を統一したり、プロジェクトへの取り組み方を確認したりすることができます。
朝礼スピーチの例文(約1分)
「おはようございます。『段取り八分、仕事二分』という言葉がありますが、これはスポーツや料理に例えると分かりやすいかもしれません。
例えば、一流のスポーツ選手は、試合という本番(仕事二分)のために、その何倍、何十倍もの時間を練習や体調管理という『段取り(八分)』に費やします。
また、美味しい料理を作るには、実際の調理(仕事二分)の前に、食材を切り揃え、調味料を合わせておく『下ごしらえ(段取り八分)』が味の決め手となります。
これは我々の仕事も全く同じです。会議の資料を事前に読み込んで自分の意見をまとめておく、訪問先企業の最新ニュースを調べておく。こうした小さな準備や下ごしらえが、会議での発言の質を高め、商談の成功率を確実に上げます。
作業に取り掛かる前の『ひと手間』を大切にすることが、結局は一番の近道になります。今日も『段取り八分』を意識して、質の高い準備から始めていきましょう」
プロジェクト会議での活用例
「このプロジェクトを成功させる鍵は、まさに『段取り八分』にあります。実行フェーズに入る前に、リスクの洗い出しと対策、各部門の役割分担を徹底的に詰めておきましょう。ここの準備の質が、プロジェクト全体の成否を決めると言っても過言ではありません」
段取り8割 名言の総括
この記事では、「段取り8 割の名言」の背景にある意味や由来、正しい読み方、そしてトヨタやイチロー氏といった具体的な実践例について詳しく解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。
ポイント
- 「段取り八分、仕事二分」は準備の重要性を説く格言
- 仕事の成果は実行前の準備の質で8割が決まるという意味
- 正しい読み方は「だんどり はちぶ、しごと にぶ」
- 「はっぷん」と読むのは時間(8分)となり誤り
- 特定の人物ではなく職人など現場の知恵から生まれた言葉
- 語源は歌舞伎の構成や石段作りの計画に由来するとされる
- 仕事で段取りが重要な理由は効率化と品質向上、遅延防止にある
- 段取り不足は手戻りや停滞といった「ムダ」の原因となる
- 「段取り」の言い換えには「手順」「手はず」「計画」「準備」などがある
- 「手はず」は関係者との調整を含むニュアンスが強い
- 関連する名言に孫子の「勝敗は戦う前に決まっている」がある
- リンカーンの「斧を研ぐのに4時間使う」も同様の意味を持つ
- ことわざでは「備えあれば憂いなし」「転ばぬ先の杖」が近い
- トヨタは「段取り替え」の時間を短縮しジャストインタイムを実現した
- トヨタの段取りはコスト削減と競争力強化に直結している
- イチローは「準備とは言い訳の材料を排除する作業」と語った
- 彼にとって準備はルーティンであり変化を察知するセンサーでもあった
- この格言はビジネススピーチや朝礼でも有効に活用できる
関連
-
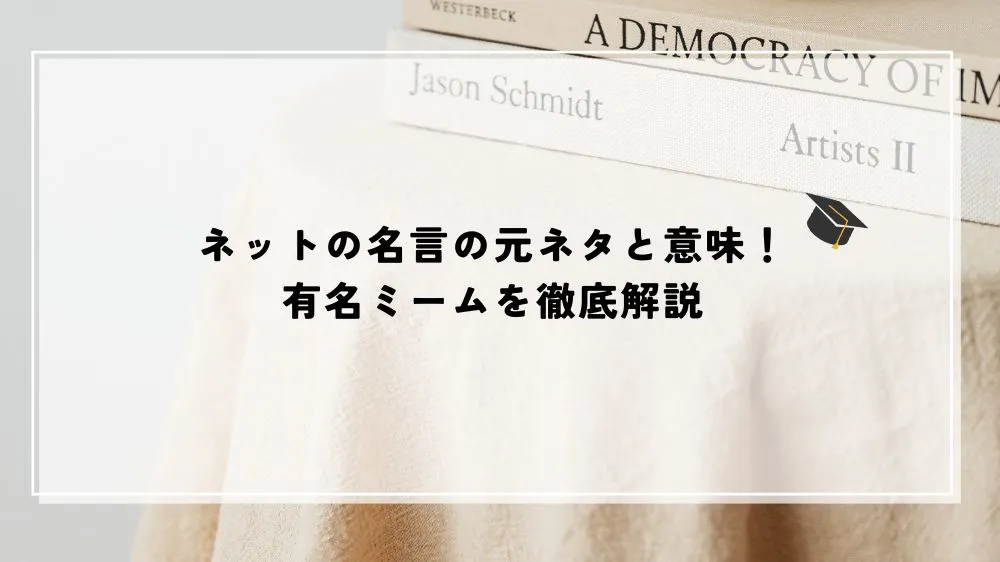
ネットの名言の元ネタと意味!有名ミームを徹底解説
2025/11/11
-

ネガティブな名言で疲れたあなたの心を癒す言葉たち
2025/11/10
-

人生を変えるセリフの名言集:活用術と心に響く言葉たち
2026/1/22
-

贈る言葉の名言を失敗なしで選ぶ極意とマナー!人生の節目で役立つ
2025/11/3
-

名言の面白い言葉に隠された人生の真実とウィットを解説
2025/11/3